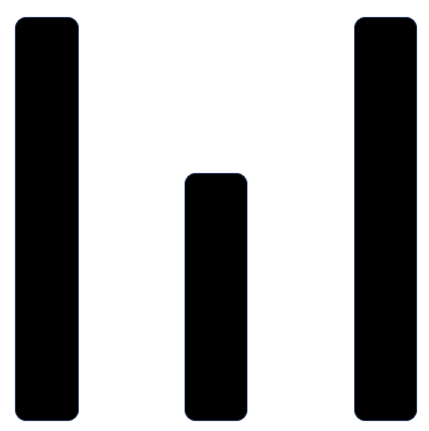積算価格(土地建物)
土地評価額: 0
建物評価額: 0
積算評価額: 0
積算価格とは?
「積算価格(土地建物)」= 土地の価値(持分) + 建物の価値(専有部)
不動産の価値を計算する方法の一つで、土地や建物のコスト(原価)を基準として算出される価格です。不動産の評価においてよく使われる基準のひとつであり、積算評価によって価格を求めるため、専門的には「積算価格」と呼ばれています。
- 1.土地の評価
-
土地の広さ、場所、相場を基に、その土地だけの価値である「更地価格」を算出します。更地価格は、国が定めた路線価を基準に、土地の面積を掛け合わせて計算します。土地の形状や立地条件に応じて、補正が行われることもあります。
- 2.建物の評価
-
建物を建てるのにかかった費用(再調達原価)から、経年による劣化分を差し引いて評価します。
この方法は、不動産の実際の取引価格や収益性を直接考慮するものではなく、「もし今この土地や建物を新たに作るならいくらかかるか」をベースにしているため、不動産の「原価的な価値」を知るのに役立ちます。
たとえば、古い建物でも土地の価値が高ければ積算価格は上がる傾向があります。一方で、築年数が古い建物は建物自体の評価が下がるため、積算価格もその影響を受けることがあります。
この評価法は、銀行融資の審査や不動産売買の参考価格を算出する際によく用いられます。
相続税路線価
土地評価額 = 相続税路線価 × 土地の面積
土地の価値を評価する基準価格。全国地価マップより検索・参照ください。相続税路線価は、積算評価で使用される路線価の中で、最も一般的に用いられる基準です。これは、国税庁が毎年公表する土地の1平方メートルあたりの評価額で、相続税や贈与税の計算に使用されます。この路線価は、公示地価(地価公示価格)の約80%を基準に設定されており、土地の評価において簡便かつ標準的な指標として広く活用されています。不動産取引や税務上の手続きにおいて、積算評価の基礎データとして役立てられます。
耐用年数
「耐用年数」とは法律で定められた建物が使用可能と見なされる期間です。建物には、法律で「法定耐用年数」という使用可能と見なされる期間が定められています。この法定耐用年数は、税務上の減価償却費を計算するための基準として用いられるものであり、実際に建物が使用できる限度を表したものではありません。例えば、木造住宅の法定耐用年数は22年とされていますが、適切にメンテナンスが行われた場合には、それ以上の期間使用可能なことが一般的です。同様に、鉄筋コンクリート造の建物は法定耐用年数が47年とされていますが、これを超えて利用されている事例は多く存在します。
- 鉄筋コンクリートRC造,SRC造:47年
- 鉄骨造S造:34年
- 軽量鉄骨造:27年
- 木造:22年
再調達原価(円/㎡)
「再調達原価」とは同等の建物を現在建て直した場合の価格を指します。再調達価格は、金融機関や保険会社が融資や審査を行う際の基準となる重要な指標です。しかし、近年の建築費用の上昇や建築資材費の変動、労務費の高騰などにより、従来の基準が現実に即していないケースが増えています。当サイトでは、これらの変化を考慮し、できるだけ汎用性の高い数値を採用しています。
- 鉄筋コンクリートRC造,SRC造:20万/㎡
- 鉄骨造S造:18万/㎡
- 軽量鉄骨造:15万/㎡
- 木造:15万/㎡